前回からの続きです。まだ読んでない方はこちらへどうぞ~
10キロ圏内の取材で浪江町へ
東京へ戻り、原子力安全保安院の会見取材を続けていた4月半ばのある日、毎日新聞の朝刊を見て驚いた。原発から20キロ圏内の取材をした記事が出ていたのだった。どうやって中に入れたのだろう?記事の署名が旧知のT記者だったので電話して話を聞くと、福島県警から毎日新聞の福島支局に取材案内があり、東京から彼が取材に出たのだという。私はすぐ松本本部長に電話し、次回の取材機会があれば東京のメディアにも教えてほしいと依頼した。2週間後、本部長から電話の着信あり。第一原発から10キロ圏内の浪江町で遺体捜索活動を行いメディアにも公開するという。「東京からも取材に行きます!いつですか?」「明日」「え?明日?」
私はその日は泊まり明け勤務だ。デスク泊まりの時は朝まで徹夜となる。一睡もせずに福島へ行くのは体力的にきつい。でも誰かは取材に行かなければ…報道局幹部にこのことを伝えると…
「まずうちのルールでは40キロ圏内の取材はできない」
「他社は20キロでも入ってるじゃないですか!絶対に取材に行くべきです!」
「線量の多い所には出せない」
「県警が普通に業務をしている場所ですよ。なぜ報道できないんですか」
長らく押し問答が続く。結局…
「廣瀬が行くというなら止めない。だが他の若い記者を出すことはできない」との結論だった。
後で聞いた話だが、幹部が話し合って「将来子供を作る若者は男女とも出せないが、年をとったベテランならいいだろう」という結論になり、最後は社長決裁だったという。
徹夜明けの私が翌朝7時、ぼうっとした頭で本社の玄関前に行くと集まったのは4人。
記者の私、カメラマン、そして空間線量の数値を常に確認する安全管理責任者が加わり、ドライバーは見慣れない若い男性だった。「初めまして、さがみです」相模モーターの社長の息子だった。社員に行けという指示は出せないという社長の判断だという。福島県内に向けて車を走らせながら「私達4人はファンタステイックフォーだよ」と映画の話をするが、皆が無反応。

カメラマンが私に聞いた。
「ねえ、今ここで大地震が来たら、僕らどうなるんだ?」
どうなるって…(そんなのわかるわけ…)だが、とっさにこう言った。
「大丈夫!県警の本部長に電話で確認したら『きょうは大地震は絶対に来ない』と言ってたよ」
真っ赤な嘘である。地震の予想など誰にも正確にできるはずはない。とはいえ私の嘘で車内にほっとした空気が流れた。
「ファンタスティックフォー頑張ろう!」
と言うと
「フォ~!」というおどけた声が続いた。
「地割れが起きたらそれより早く運転すりゃいいしね」
社長の息子の相模君が映画の一場面を思わせるように言った。不安になっても仕方がない。その時はその時。しばらく走っていると荒野のような田園風景が広がる。
「馬だ。馬がいる」
え、馬?
「違う、牛だ!やせた牛!」
家畜からすっかり野生化した牛が猛スピードで走っていた。カメラに撮って!と叫ぶが牛はあっという間に視界から姿を消した。
「…撮れていればよかったなあ」
しかし追いかけている時間はない。空間線量との闘いで、急いで集合場所に向かわなければならなかった。県警が指定したJビレッジで取材陣全員が用意されたタイベックススーツに着替える。空気が入らないように手袋と袖の周りをガムテープでぐるぐる巻きにする。防護マスクが息苦しいが、外すわけにいかない。東京からはフジテレビやTBSやNHKのクルーの姿も見える。テレビ朝日は途中の飯館村付近で線量が30マイクロシーベルトを超えたため、本社命令で撤収させられたという。途中まで来たのに帰らなければならない無念さは他人事ではなかった。私達も飯館村を通った際、線量計があと一歩のところで毎時30マイクロシーベルトに届こうとしていた。安全管理責任者が「30を超えたら引き上げますよ」と宣言し、みんなで「どうか上がらないでくれ~」と手を合わせて祈ったのだった。幸い30を超すことなく現場に来られたという経緯があった。
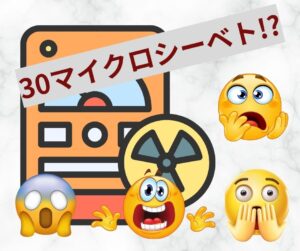
県警本部長の背中
県警の先導で各社のクルーが車列を組みながら取材現場の浪江町へと向かう。緊急避難から47日間が経過していた。車が一台も走っていない道路で信号だけが点滅していた。市街地を抜けると普通の民家が並んでいた。庭には物干し竿があり、色とりどりの洗濯物がひらひらと風になびいていた。子供服、お父さんの下着、シーツ…この家にいた人は洗濯物をとりこむ余裕もなく慌てて家を出たに違いない。避難は一時的なものだと思いこんでいたはず…そう思うと胸が熱くなった。
捜索現場に到着すると防護服姿の警察官達が懸命に捜索活動を行っていた。
線量計の数値は飯館村よりはるかに低い、0.5マイクロシーベルトだった。
前方には瓦礫が散乱している10メートル四方のくぼ地があった。私が一人でくぼ地に降りてカメラが離れた場所から撮影すれば画角的にも現場の状況をわかりやすく伝えられる。レポートを取る場所はそこしかない。カメラマンは同意しつつも、こう言った。
「瓦礫があって危ないから降りる時注意してよ。防護服は絶対に傷つけないでよ。大丈夫?」
「大丈夫!」(当たり前でしょ)と敢然と一人向かったのはいいが、慎重に降りていたはずが…あれ?ズルズル……ビリ‼なんと斜面を降りる時に足を滑らせてしまい、木材から飛びだしていた釘に防護服のズボンをひっかけたのだ!あわてて振り解こうとしてズボンの表面に穴があいた!
ガムテープでふさいだ意味がなくなったのだが、ショックを受けている暇はない。
グラグラ揺れる瓦礫の上に立ってマイクを握る。
「ここは福島第一原発から7キロ地点にある浪江町の遺体捜索現場です。福島県警による捜索活動が朝から行われています」

カメラマンの所へ戻って防護服が破れた箇所を見せると
「だから注意しろと言ったんだよ‼」とぷりぷり怒りながら割けた箇所をガムテープでふさいでくれた。
福島県警の警察官が第一原発の排気塔が見える場所まで案内してくれた。
「あそこにいるのがうちの本部長です。後ろに排気塔も見えます」
指さす場所を見ると白い防護服の警察集団の中に一人「福島県警本部長」と黒マジックで書かれたガムテープを背中にちょんと張った本部長の姿が目にとびこんできた。
「本部長はいつも我々の現場に来てくれるんですよ。指示もいつも的確ですごい人です」と誇らしげに言う。広報担当者によると松本本部長は地震発生直後に情報収集して津波の危険性を住民に知らせる避難指示をいち早く発令したという。また避難所の開設や支援物質の確保にも迅速に取り組む一方、一線で活動する警察官の健康を常に気づかっているという。本部長は背中を少し丸めて立っていた。その背中を今も思い出す。県民の生活を守るという責任者としての意志が背中からにじみ出ていた。

視聴者からの電話
本社に戻り、夜の放送を無事に終えた翌日、視聴者から一本の電話がかかってきた。浪江町に住む人だった。涙声で彼女は言った。
「故郷が今どうなっているのかわからなくて不安でしたけど、テレビを見て涙がとまりませんでした。取材に行っていただいて本当にありがとうございました…」
テレビの記者は視聴者から直接お礼を言われる経験がほとんどない。私は受話器を置いたあとも、嬉しくてしばらくぼうっとしていた。徹夜明けの福島入りは体力的にきつかったけど、行って本当に良かったと心から思った。誰のために何のために取材をするのか?それを待っている視聴者のためなのだ。
当時も今も日本テレビの報道局には「科学部」という専門の部署がない。原発事故後、原発班という取材グループが出来て、私はキャップとなり、私よりはるかに優秀な後輩記者達と原発事故の課題に関わり、事故調査委員会を取材することになるのだが、きっかけとなったのは政府関係者との電話だった。
記者なら現場に行け!
事故直後から官邸、原子力安全保安院、東京電力の3か所で連日記者会見が行われたが、情報は混乱、記者会見は大荒れだった。3月17日午後には陸上自衛隊のへりが原子炉建屋上空から必死の放水を試みるが効果のほどは疑問だった。

一人の政府関係者にようやく電話がつながると、彼は激怒していた。
「イギリスのタイムズの記事、読んだ?(いや読んでません)自衛隊へりが放水している写真を使ってツーリトルツーレイト【(too little too late)=今更手遅れ】って揶揄してるんだよ!福島第一原発の現場もすべての政府機関も皆が寝る間もなく必死にやってる時にあんまりじゃないか。日本のマスコミだってそうだよ。日本の非常時なんだ!記者なら批判するだけでなく現場に行けよ現場に!」
そうだ。私ははっとした。記者は現場に行くのが仕事だ。
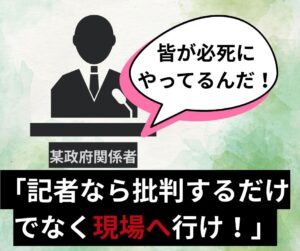
改めて記者の原点に気づかされたような気がした。次の日から私は自主的に原子力保安院の会見に出て放射能について勉強し、福島へ取材に出る機会を待ったのだった。未曽有の原発事故。先がどうなるか見えない時に人間の行動にはいくつものパターンがある事を知った。現実逃避してパニックに陥る人、逃げる人、責任転嫁する人、批判だけして何もしない人…そんな中で被害を最小限に食い止めようと全精力を注いで取り組んできた福島第一原発の現場作業員や多くの自治体関係者、官邸からの一方的な横やりに対して的確に海水注入やベントを実施した吉田所長の存在がなければ日本はもっと甚大で深刻な被害を受けたことは明らかである。
人知を超える発展を遂げたAIでも未曽有の事態には対応できない。それができるのは人間だけなのだと心から思いたい。


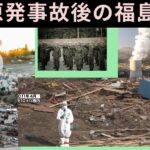
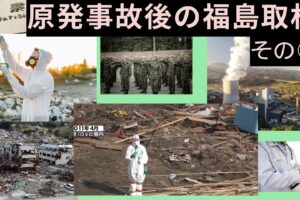





コメントを残す