こんにちは。テレビ記者38年、廣瀬祐子です。忘れることのできない取材の一つが2011年の東日本大震災で、津波による甚大な被害に加え、原発事故という複合的な大災害に直面した福島での取材です。事故発生の1週間後と1か月後に福島へ取材に入った時の思い出を2回に分けて投稿します。
地図を頼りにあちこち取材
取材クルーは全員東京組で土地勘がない。地図を片手に福島市やいわき市など思いつくまま向かう。行きつく先に農家があれば農家へ、警察署があれば警察へ、病院があれば病院へ、避難所があれば避難所へ向かう毎日だった。陸上自衛隊が崩壊した建物からがれきを撤去している現場も取材した。周辺には放射性物質を除染する為の簡易な小屋が設置され、隊員達は長靴をホースの水で丁寧に洗い流していた。通常の災害派遣の任務に加えて放射能汚染対策も講じなければならない。空気中の線量計の数値は一時間あたり0点3マイクロシーベルトで数値は思ったほど高くはないことにほっとした。
福島赤十字病院を取材した時は。ぼさぼさの髪をした若い男性医師が取材対応してくれた。次々と救急車で急患が運ばれてくる。交通事故、腹痛、症状は様々だ。医師は診察の前に患者の体から放射性物質を洗い流す処置もしなければならない。通常の診察の倍の時間がかかっていた。診察が終わると病院の外で彼はうまそうに煙草を吸っていた。放射能+煙草…体に良さそうでは…ない。
「10人くらい医者が逃げちゃったんで人手が足りなくて…」と言う。
「それは大変ですね。放射能は怖くないですか」
「う~ん…怖いって思う余裕もなくて仕事してたんだけど。実は2,3日前、通勤に使うバイクの荷台にうっすら白い埃が溜まってたんですよ。それ見た時、『あ、放射性物質が溜まっている所にいるんだ!』と思ったら急に怖くなっちゃって…」
彼は押し黙る。私も言葉がみつからない。
「仕事だから、じゃ…」
煙草を素早くもみ消した彼は病棟に戻っていった。背中を少し丸めていた姿が目に浮かぶ。自分のことより患者を優先させる医者の姿がそこにあり感銘を受けた。この時は彼の言った恐怖を痛感する出来事が自分にも突然降りかかるとは思いもしなかった。
突然襲う恐怖

全国各地から続々と支援物資がトラックでJビレツジに運ばれてくる。それを警察や自治体が仕分けして避難所に届ける様子を取材した時の事だ。取材を終えて引き上げる際には、職員がガイガーカウンターで我々の靴底の数値を図る。運動靴は装置を向けられるとピーピーピーと大きな音を発していた。
「はい、オッケー」と言われそのままホテルに戻ったのだが、夜のニュース番組が終わると、後輩記者から電話がかかってきた。私の後任として福島入りする次の記者が決まらず、本社が人選に困っているという話だった。彼は言った。
「廣瀬さんも早く東京に戻らないとばい菌扱いされますからね」
「え??」
電話を切り、足元を見ると部屋の中でも外靴を履いたままだった。この靴で室内を歩き回っていた…と思った途端、部屋中に放射性物質が漂っている錯覚にとらわれ、目に見えない放射能の恐怖がどん!といきなりのし掛かってきたのだ。気づかないまま被害に遭っているのでは?不安な気持ちを誰かに話したいが共有できる人がいない!東京にいる家族や友人に電話して心配をかけるわけにもいかない。孤独感に襲われた私は、いてもたってもいられず取材先の福島県警の本部長に電話をしたのだ。電話に出た松本光弘本部長(後の警察庁長官)は落ち着いた声でこう言った。
「今、廣瀬さんの部屋の空間線量はいくつですか」
「え、ああ…0.4マイクロシーベルト」
「問題ないですね。私のところは今0.8マイクロシーベルトですよ。福島市の方がいわき市より高い。そもそも靴表面の汚染は気にしなくていいです。大事なのは空気中の放射性物質の量ですから」
そうだ、そうだった。福島取材前に勉強してきたはずなのにパニックになっていた。
「本部長は放射能、怖くないですか」
「ちゃんと数値を把握していれば怖くないです。」
松本光弘県警本部長は原発事故直後から放射能の専門家を長崎医大から福島県警に呼んで全警察幹部に3日間の講義を受けさせたという。放射能を正しく理解するためだ。さらに警察庁を通じて全国警察に保管されていた線量計を福島県警に集め、外周りの警察官に配布、線量を測定しながら日常の警察活動にあたらせていたのだった。おかげでどの自治体の機関よりも福島県内の放射性物質の量について正確な数値を日々の警察活動の中で蓄積しているという。
「爆発事故当時の風の向きで原発近くよりもむしろ西側の飯館村の方が線量が高いんですよ」と彼は現状について説明してくれた。その冷静で科学的な分析に私は感銘を受けた。松本本部長のおかげで私の恐怖は消えていた。
農作物の風評被害

車を走らせるといちご農家があった。若い夫婦と幼い二人の子供の家内農業。丁度これから収穫するというので取材させてもらう。つぶつぶ大ぶりのイチゴを挟みでカットして丁寧に籠へと入れていく。しかしその表情が暗い。出荷のめどがたたないという。
農協が福島の農産物を引き取らない。市場に出しても放射能が含まれているという理由でまったく売れない。風評被害の影響は深刻だった。専門家が農作物への影響をどんなに否定しても、放射能汚染の影響を受けていない東京ですら水道水を忌避する状況下で福島の野菜が売れるはずがない。放射性物質は洗い流せば健康への影響はないと専門家が強調しても信じる消費者は少なかった。
「それでも収穫しなければしようがないんです」彼は黙々と収穫をし続けていた。その背中もやはり丸かった。
取材できない悔しさ

また車を走らせていると今度は酪農農家の男性に出会う。
「うちの牛、えさがなくて痩せてきたんだ。すぐ近くだから取材してほしい」という。もちろん!と取材に向かおうとすると地図で取材場所を確認していたスタッフから待ったがかかった。
「うちの取材制限区域外なので取材に行けません」
「え?どのくらい?」
「20~30メートルくらいですが…」
「そのくらい、別にいいでしょ!」
「いや!ダメです。本社から絶対にだめだと念をおされました」
そこで電話で本社と交渉するのだが、答は同じだった。すぐ目と鼻の先だと訴えても
「ルールを守ってください。そうやって現場がルールを破ると収拾がつかなくなる。」と安全担当デスクから注意される。
実際に毎日そこで生活している人達がいるというのになぜメディア側が取材に規制をかけるのか。いらだちが募る。現場の判断を信じてほしいと再度食い下がったのだが、こう言われて断念する他はなかった。
「廣瀬さんの独断でスタッフを危険にさらすんですか!」
ああ…一人でデジカメをもって現場に行きたいい!と心からそう思い、デジカメを持ってこなかった自分の先見性のなさを心から悔んだのだった。(現在ならスマホでいくらでも一人で取材に行き、撮影できただろうと思うけど、)
「え~すぐそこなのに?…」と酪農農家のおじさんは残念そうに言った。
避難所での忘れられない光景
福島取材から1週間ほどたった夕刻の光景は忘れられない。この日も福島市役所での取材を終えた帰り道だった。人気のない小学校の校庭の脇を通ると校舎から明かりが漏れていた。
「誰かいる。取材に行こう!」とりあえず私だけ取材交渉のために向かうと、3階建ての校舎全体が避難所となっていた。体育館で夕食の支度をしていた世話役の女性が快く取材を受け入れてくれる。
スタッフを呼んで改めて教室内に入った途端、その女性がマイクを手に声を張り上げた。
「みなさ~ん、日本テレビの方達がわざわざ遠くから私たちの取材に来てくださいました!お行儀よく配膳台の前に並んで下さ~い」
事件取材が多かった私は取材先からこんな風に感謝された経験がほとんどない。配膳台の前には被災者が家族単位で整然と並び、それぞれ地区ごとに助けあいながら食事をとり分けていた。その様子を撮影していると、被災者家族の一角にいる小学校低学年の少女の姿が目に入った。雑然とした床にはミカン箱が置かれ、それを勉強机の替わりにして一心不乱に宿題をやっていたのだ。

(あれを撮って)とカメラマンに目で合図を送ると彼はすでにカメラを回していた。少女の健気な姿を見ると涙がこみあげてくる。隣の録音マンも涙目だった。彼はマスクをずりあげてそっと涙を隠した。後に世界各国から称賛された純朴で誠実な東北の被災者たちの姿をそこに見たのだった。

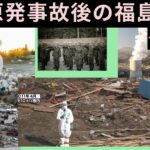







コメントを残す