こんにちは。テレビ記者38年やってました。廣瀬祐子です。アカデミー賞の脚本賞にノミネートされていた「セプテンバー5」を見ました。
「セプテンバー5」の感想
1972年9月5日に発生したミュンヘン五輪でのパレスチナゲリラによるイスラエル選手団人質テロ事件。人質救出に失敗し、人質全員が死亡するという痛ましい惨事となったこの重大事件をアメリカABC放送の中継スタッフの視点でドキュメンタリーのように再現する技術が素晴らしい。何よりも緊迫した状況の中で一瞬の判断が迫られるテレビマンの使命感と葛藤を描いた上質のドラマに仕上がっている。
平和の祭典のはずのオリンピックでスポーツ中継のスペシャリスト達が遭遇した未曽有のテロ。最初は「銃声の音?まさか?」という疑問から、(ドイツ人の優秀な通訳の機転もあり)情報が断続的に入ってくる。そしてイスラエル選手団が何者かに襲撃され、コーチが射殺されたという衝撃的な情報な展開に騒然となる。その事実を知ったときのスポーツ局の責任者の表情が印象的だった。オリンピックで第二次世界大戦後の復興と平和を強調するドイツで起きた理不尽なテロ(しかも犠牲者は再びユダヤ人)に対する憤りとそれを伝える覚悟を決めた表情。直後にABCの本社から「テロ事件だから報道が仕切る。スポーツ局は撤退しろ」との指示が飛ぶが、「地球の裏側(=アメリカ本社の報道)にいる彼らではなく目の前にいる我々が仕切る」と断固拒否。平和を愛する中継スタッフの意地を見せた。

どこまで生映像を中継するのか、テロが進行する現場(周辺)から生中継するなど過去に経験した事などない。犯罪者側を利することになるのでは?でも世界中に報道しなければ…という葛藤。一瞬の判断を迫られる緊迫感が伝わる。錯そうする情報の中で何が正しいのかをぎりぎりまで裏を取り続ける作業は報道の原点だが、見ている私も胃がキリキリ傷んだ。 テレビ報道はさまざまな技術のプロによる力の結集だが、記者の仕事は情報を収集して正しい情報を伝えることだ。テロは全く予期しない時、予期しない場所で起こる。1972年にミュンヘンオリンピックで起きたテロ事件は、時も場所も形も変えて23年後の1995年3月20日に東京のど真ん中でも起きた。通勤・通学客で混雑する朝の地下鉄車内だった。
地下鉄サリン事件の朝
午前8時15分すぎ、当時の私は警視庁クラブで泊まり明け勤務だった。突然、消防無線がけたたましいがなり声をたてる。日比谷線築地駅構内で異常発生!負傷者多数出ている模様…霞が関構内で…神谷町駅で…、千代田線国会議事堂前で…第一報の情報は錯綜するのが常だが、こんなにも現場が特定できない(その時はそう思った)のはおかしい。一体本当の現場はどこ?消防に確認すると「同時多発的です!ガス漏れかなんか…」と広報が答える。本社に一報。これが世界初の化学兵器テロと(後に)記録される地下鉄サリン事件の報道の始まりだった。警視庁本庁の9階には新聞・テレビ・通信社の常駐社用に記者クラブが置かれ、各社うなぎの寝床状のスペースが割り当てられている。記者は夜中に発生する事件事故の取材対応の為、常に24時間体制だ。午前8時半、警視庁広報から「総合通信指揮所を開設します」と連絡が入る。都内の110番通報がすべて見渡せる普段は非公開の指揮所を記者に開放するという。
有毒ガスの正体は…
こんなことは前代未聞だった。大変な事が起きている!警視庁クラブには中継デイレクターや記者達が続々と到着してくる。取材しているうちに「被害者の目に縮瞳があり神経系のガスかもしれない」との情報が入ってきた。「神経系?たとえば?」「ホスゲンとか…」ホスゲン!?広範囲に?何がなんだかわからないまま、ワイドショーのニュース枠に「詳細不明だが、現場周辺で有毒ガスが発生している模様、ホスゲンの可能性あり…」との原稿を急いで出稿した。この時点ではガス漏れによる事故だと思い込んでいた。そして午前11時、刑事部捜査1課の寺尾課長の定例会見が始まる。

サリンと判明!
1課長室は詰めかけた記者達で立錐の余地もない。私は会見の一報を伝える為、記者集団の最後尾で出口に一番近い場所に立った。厳しい表情で入室した寺尾正大課長は椅子に座るや否や一枚の紙を読み上げる。
「地下鉄車両内に散布された物質はサリンと判明。警視庁は本日、無差別大量殺人事件と断定して捜査本部を設置した。以上!」サリン?その瞬間全身に雷が走った。松本で多数の死者を出したあのサリンが地下鉄に?有毒ガスの正体はサリンだったのか!「無差別大量殺人」という言葉を現実世界で聞くのも初めての事だった。いつもは慎重な物言いの課長が「断定」という言葉を使うのも初めてだ。
考えるより先に私は反射的に会見場を猛ダッシュで飛び出した。6階から9階の記者クラブまで階段を2段飛ばしで駆けあがり、日本テレビのボックスに駆け込む。
「サリン!サリンだって!サリン!」
ボックス内の空気がまさか!と一変する中デイレクターが叫ぶ。「あと20秒で警視庁中継です!」え?何?ちょっと待って!息が切れているし原稿もできていな……
「はい!キュー!」息を整える間が全くなかった。
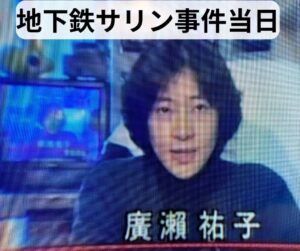
この時のレポートがテレビメディアの中で最も早くサリンを伝えた速報だったと後に言われるのだが、ただ中継のタイミングが他局より早かっただけのことだ。私は一刻も早くサリンが原因だという事実を伝えなければという気持ちだった。(ホスゲンは間違いだったと言う気持ちも…)本社からは「興奮しすぎだ。もっと落ち着け」と言われたが、階段を二段飛ばしで全速力で走れば誰だって息が切れる。そんなことより続報を!記者会見でその後どんな情報が出たのか?後輩記者達の戻りを待った。しょんぼりと彼らが帰ってくる。「課長は?何て?」「いや…他には何も…」「なんで質問しないの?!」苛立ちから怒りがさく裂した。すると…「もちろん皆で色々と質問しましたよ!だけど何を聞いても1課長は『今出て行った先輩記者を見習え、すぐにサリンだと伝えるんだ』というだけで僕らの質問には一切答えなかったんですよ!」後輩記者がため息をつく。
一刻も早く報道すること!
当時は今のようなSNSはなかった。テレビでの速報が一番早く世の中にサリンの事実を伝える手段だったのだ。被害者が運び込まれた病院では何が原因なのかわからないまま医者たちが懸命の治療にあたっていた。寺尾課長は一刻も早く情報を病院に伝えたいと考え、会見をすみやかに終わらせたかったのだ。後年、寺尾課長と何度も酒を酌み交わしたが、「捜査をするのは僕らの仕事。報道するのは君らの仕事。協力しあう事など決してないが、サリンだとわかった時だけは別だった」と語っていた。私はその後も上九一色村での強制捜査や信者の逮捕、教祖の公判等一連のオウム事件を取材したが、その頃は異常な宗教団体による凶悪事件と捉えており、「テロ」という認識はなかった。その後の捜査でオウムがへりで東京上空からサリンを撒き、国家の転覆を図っていた事が判明、警察組織全体を震撼させた。地下鉄サリン事件が世界で初めて都市部で起きた化学テロだという認定がなされたのはそれから数年後の事だ。
イスラエルの諜報機関トップに質問
建国当初から周囲を敵対国に取り囲まれて誕生した国・イスラエル。その諜報機関のトップが日本のメディアを対象に会見するという貴重な機会があり、取材に行ったのはサリン事件の10年後だった。
建国当初からイスラエルは遠い国との友好的な外交を構築することで安全保障を確保してきたと外交の重要性を語ったのだが、私が最も感銘を受けた箇所は、日本赤軍の岡本公三らによって引き起こされたテルアビブ(ロッド)空港・無差別銃乱射事件のその後の話だった。(ちなみにこの銃乱射事件の3か月後に冒頭のミュンヘンオリンピックでのテロ事件が発生する)大惨事の舞台となったテルアビブ空港は、独立の父であり初代首相のベングリオンの名前を取ってベングリオン空港と名称を変えていた。空港内には3000台を超すカメラが常に稼働し、世界一警備が厳しいと言われる国際空港だという。
3000台!テロの未然防止にどれだけ役に立っているのだろう。日本でも参考にできるのだろうか。私は質問した。「3000台の監視カメラによってどれだけのテロが未然に防げるものですか?」彼の答えは明確だった。「カメラは事後の確認や追跡のためのもの。未然に防ぐことは期待できません」そしてこうも言ったのだ。ベングリオン空港には常に家族連れやカップルに変装した工作員が常時ぶらぶらと徘徊しており、不審者をチェックしているという。現実に老婆や旅の若者に扮したテロリストを工作員が見抜いて逮捕したという。私はさらに聞いた。「見抜くために重視しているポイントは何ですか?」彼は静かに答えた。

「身なりや行動などですが、それだけでは見分けられません。最終的には目です。テロリストは目を見ればわかります。工作員はそのように訓練されています」
高性能の機械ではなく人間の目でテロリストを見抜くというのだ。敵対国に囲まれているイスラエルには四方を海に囲まれている島国日本にはない厳しい現実があった。私は彼の目を見、彼も私の目を見て視線が交差した。私には想像もつかない過酷な現実を生きてきたような目だった。卑劣なテロ行為をどうやって防ぐのか。地下鉄サリン事件が発生した30年前には捜査のために防犯カメラを使う手法はなかった。警察が防犯カメラの映像を犯罪捜査に使うようになったのはオウム事件の後のことだった。いつの時代もテロを起こすのは機械ではなく人間なのだ。(SF映画は別として)人間が起こすテロを防止するのもまた我々人間の役割であり、報道の役割なのだと思う。

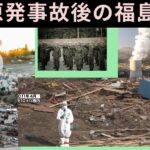







コメントを残す